こんにちは。会社員ブロガーのしゃちです。
ぼくは、あまりしゃべりが上手くありません。
しゃべる際ハキハキとしゃべることが苦手で、聞き返されることがよくあります。
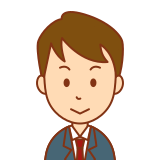
今度のプレゼンの資料について相談があるのですが。
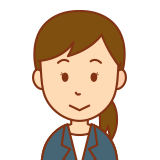
え?ごめん、もう一度おねがいします。
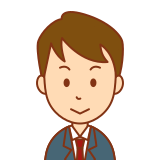
(またか。。。)
通る声、はきはきした声、内容がスッと入ってくる声の人にずっと憧れています!
今回は、声楽家として活躍されている國土潤一さんの著「歌の本 歌の好きな人と歌が苦手なあなたに」を読んで、歌だけでなく、発声方法について知っておくべき内容が多いことに気づきました。
普段何気なく行っている「声を出す」ことについて、少し意識するだけで良い声に近づける。
そのために、知っておくべき3つの方法をご紹介します。
この記事から得られること
✔良い声の獲得
✔聞き返されるストレスからの解放
✔自信につながる
声帯負担の少ない発声方法を手に入れる
普段しゃべるときに、声帯への負担を意識することは少ないと思います。
しかし、声帯とは喉ぼとけの少し下にある粘膜に覆われたV字型の筋肉で、成人男性で15mm、成人女性で9mmほどの小さくてデリケートな筋肉です。
鍛えてマッチョにすることもできないため、声帯の負担を減らしてあげる必要があります。
そのためには、舌根の余計な力を抜くことが効果的です。
力が抜けた状態とは、よだれをたらしてうたた寝している状態の舌をイメージしてください。
舌をだして、左右に傾けたときに、下の重さでゆっくり移行するのを感じてみてください。
この状態が、余計な力が抜け生体への負担が少ない理想的な状態です。
舌の力を抜くことを覚えたら、次は発音について。
発音は、口の形で2系統に分類されます。
「あ」系と「お」系です。
「あ」系は、「あ」、「え」、「い」で舌を少し上げるだけで発音ができます。
「お」系は、「お」と「う」で。舌の若干の前後だけで発音ができます。
つまり、
①2つの発音のそれぞれの境界線を自分なりに把握しておく
②舌の動きはなるべく少なくする
この2つを意識することで、声帯の負担が少ない、効率的な発声が手に入ります。
✔舌の力を抜く
✔発音を2つに分け、なるべく舌の動きを少なくする
よく通る声を手に入れる
よく通る声にするためには、しゃべるときの口の形も大切です。
山登りで見晴らしがよい高台にきたとき、つい「ヤッホー」と叫びたくなりますよね。
その際、口にメガホンのように手を添えて叫ぶことで遠くまで声が響いていきます。
この「ヤッホーの空間を口で作る」ことが、よく通る声にするためのコツです。
口の奥の上部分に、軟口蓋と呼ばれる部位があります。
舌で口の上の部分を奥になぞっていくと柔らかくなる部分があります。ここが軟口蓋です。
ここを上げることによって、口腔内の奥に「縦長の空間」が出来上がります。
こうすることで、喉に負担が少なく、よく響く声を発生する形を手に入れることができます。
✔ヤッホーの空間を口で作る
母音をなめらかに発音する
最後は、母音を意識すること。
話すときは、母音が、滑らかにつながるように意識することで、言葉が豊かになります。
特に、語尾の母音をしっかりと発音することで、はっきりとした良い印象を与えることになります。
歌う時にも、母音を意識することで上手に歌えるようになります。
そのために有効な練習方法として、歌詞から子音を取って母音だけで歌う練習が紹介されていました。
これ、実際にやってみたのですが意外と難しくて面白いので是非チャレンジしてみてください。
✔母音をしっかりと発音する
まとめ
最後に、「歌の本」に書かれていた素敵な言葉を紹介して終わりにします。
人は技術の習得に夢中になると、大事なことを見失うことがある。
歌の本,(著)國土潤一,p118
大事なのは、今ある自分の「技術」でできる最高の「演奏」をしようとすることなのだ。
練習が目的にならないように気を付ける必要がありますね。
今を楽しむ余裕を忘れず、日々頑張っていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。





コメント