こんにちは。会社員ブロガーのしゃちです。
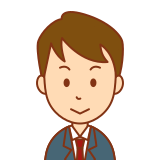
ベランダで洗濯物を干すだけなんでもったいない
ベランダに裸足で出られれば、生活空間が広がります。
ぼくは毎朝、ベランダにあるハンモックで瞑想しています。
1日の中で、穏やかにすごせるベランダ時間がとても好きです。
ベランダを活用するメリットは以下のとおり。
✔朝気持ちよく太陽を浴びてセロトニンを促進
✔ベランダに裸足ででられる
✔読書や食事など、好きなことが外気分で味わえる
洗濯物を干すだけにしておくのはもったいないと思いませんか?
おうち時間も増えて、生活空間の見直しが進むいま。
ベランダを見直して快適空間を手に入れちゃいましょう。
ベランダDIYの手順


ベランダのDIYは3ステップあります。
1.ウッドデッキと人工芝を敷く
2.フェイクグリーンのカーテンを設置する
3.室外機を隠す
ウッドデッキと人工芝を敷く
手軽にウッドデッキを敷くのにおすすめなのが、IKEAのウッドパネルです。
連結タイプで工具もいらずに簡単に敷くことができます。
ウッドパネルのサイズは30cm×30cmなので、必要な枚数の計算も簡単です。
ベランダの縦と横のサイズを計測し、何枚必要なのかを把握しておきましょう。
うちの場合、2LDKで窓が2面で、36枚で十分足りました。
1人暮らしのベランダなら、18枚あれば十分敷き詰められると思います。
敷き詰め終わったら、仕上げにワックスがけをしてあげると長持ちします。
ワックスがけと言っても、ワックスシートで拭くだけなのでとても簡単です。
このひと手間を惜しむと、木の劣化が早くなってしまうので、頑張りましょう。

ここでひと段落。おつかれさまです。
ウッドパネルを敷き終わったら、排水溝などのウッドパネルが敷けない部分を人工芝で覆いましょう。
人工芝を選ぶポイントは、以下のとおり。
✔ロールタイプ
✔水はけのよさ
✔カットのしやすさ
人工芝には「ロールタイプ」と「ジョイントタイプ」があります。
ジョイントタイプは、パネルを組み合わせるだけなので敷くのは簡単です。
しかし、ジョイント部分に線が入り目立ってしまうデメリットがあります。
見た目を重視するなら、ロールタイプがおすすめです。
また、選ぶうえで一番重要なのが「水はけのよさ」です。
これは、人工芝に透水穴があるかどうかを見て判断します。
水はけが悪い人工芝は、雨が溜まり腐ったり劣化してしまうので、コストがかかってしまいます。
ぼくも使っているおすすめの人工芝はこちら。
水はけもよく、カッターで簡単にカットもできるので、ベランダにぴったりでした。

これで土台は完成!!
フェイクグリーンのカーテンを設置する
次は、フェイクグリーンのカーテンを設置します。
設置する理由は以下のとおり。
✔近隣からの視線防止
✔おしゃれな雰囲気の演出
✔手入れ不要
都会の低層に住んでいるなら、周囲からの視線が気になるところ。
お隣さんとの距離が近い場合も同じです。
ベランダで快適に過ごすためには、視線を気にせず好きなことがしたい!
それには、フェイクグリーンのカーテンを設置することをおすすめします。
フェイクグリーンでも、かなり本格的な見た目になっています。
これを設置するだけで、視線を気にせず、緑に囲まれた素敵な空間が手に入ります。
高層階や周囲がひらけていて視線が気にならないなら、お隣とのパーテーションを隠すために使うのもおススメ。
ぼくのうちは、4階で視線も開けているので、パーテーションを隠すために使っています。
設置する際は、両面テープフックなどを活用しましょう。
外でも使える便利フックはこちら。
ただし、賃貸などの場合、はがす際に跡が残ると原状回復費用がかかる場合があるので注意しましょう。

ベランダDIYもいよいよ大詰め!!
室外機を隠す
最後は、室外機を隠しましょう。
隠す方法はいろいろ。
隠すためのアイテムを活用するもよし。
自分で箱をDIYするもよし。
ぼくは、余ったツーバイフォー材を組み合わせて目隠しをDIYしました。
商品を買うと結構かかるので、楽しみながらDIYしてみるのが良いと思います。

これで完成!!
まとめ
ベランダDIYをしたことで、ベランダでの過ごし方が大きく変わりました。
洗濯ものを干すだけの場所から、気持ちよくリラックスできる場所に。
ぼくのうちでは、洗濯乾燥機を使っているので、実は干すこともあまりないのですが。
ベランダを自由にコーディネートできるのも、洗濯乾燥機のおかげです。
干す作業が無くなったことで、家事の時間がかなり減り、自由時間とストレスのない暮らしを手に入れました。
洗濯乾燥機のメリットは以下に詳しく書いてあります。
おうち時間で家で過ごす時間が今後増えていくと思います。
家の中にリラックスできる場所があると、気持ちにもメリハリがつきます。
リラックス空間としてのベランダ、ぜひ生活に取り入れてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。






















コメント